
市寸島比売命の神名を、ウィキペディアでもう一度確認してみよう。「神に斎く島の女性(女神)という意味。」島とあるが、半島でも島であるから、辺津宮に鎮座している市寸島比売命は、そのまま島の女でいいのだろう。なんとなくプッチーニ「蝶々夫人」で、船出する男を見送り、再び戻るのを見守る、島に斎く女のイメージに近いのかもしれない。つまり、そこには航海の安全を願うものであるのだろう。確認はしてないが、宇佐家の伝えによれば、御許山の祖宇沙都比古の墳墓に鎮座するのが宇沙都比売、実は市寸島比売命という事らしい。宇佐では、宇佐神宮の東南に聳える宇佐嶋に天降ったとされているが、宇佐嶋とは御許山の事で、山は森とも言い、嶋とも言ったようだ。つまり嶋に天降ったとは嶋に斎いたという比売神であり、その名の持つ意味の通り市寸島比売命なのかもしれない。

瀬織津比咩を祀る早池峰神社には、岩手県指定天然記念物となっているイチイの木がある。「聞き書き遠野物語」で有名になった内藤正敏氏は「ウッコの立ち枯れた葉を燃やすと線香の香りがする。」と語り、このイチイ(ウッコ)の木が古代シャーマニズムと関係しているのではという見解を示している。またイチイの木は水を吹くという伝承があり、防火としての樹木として信仰されたようだ。そういう意味合いから、水神である早池峰の神を祀る早池峯神社には適した樹木なのであろう。

ところでイチイの木の転訛名ウッコだが、東北では牛を「ベゴ」と呼び、それに「コ」を語尾に付け「ベゴッコ」などと呼ぶ。他にも「娘ッコ」など、いろいろなものの語尾に「コ」を付ける風習がある。恐らく「ウッコ」もそうだろうと思っていたが、調べるとフィンランド神話で、天空・天気・農作物とその他の自然の事象を司る神をウッコ(Ukko)といい、フィンランド語の「雷雨 (ukkonen) 」は「ウッコネン」と呼ぶらしい。そのウッコ神が妻と連れ添っている時には雷雨が起こるとされ、フィンランドのウッコ神とウッコの木がどう結びつくかわからぬが、早池峯神社境内に夫婦のウッコがあるという事は、水神でもあり雷神にも繋がる早池峰神との共通点を感じて面白い。東北の文化は北部ヨーロッパの影響もあると云われるので、ウッコの木の語源がフィンランドだとしてもおかしくはないのかもしれない。
実は「女神は木に斎き、男神は石に斎く。」という説がある。確かに三保の松原の松の木に天女が降り立った話のバリエーションは全国に広がる。しかし海幸彦である火照命は、釣針を探しに綿津見の宮殿へと行き斎つ桂の木に登った時に豊玉姫と出逢っている。もしかして火照命という男神が斎いた木にも感じるが「古事記」の解説を読むと、桂は井の辺りに生える水の聖木であるので必ず「斎つ」を冠するとある。つまり海神の宮の井に生えている桂は水神の樹木なので「斎つ」とは水神が斎つという意味になる為、火神である火照命が斎いたわけでは無いようだ。その後に海神であり水神の娘、豊玉姫と結ばれる事から、ここでも火と水の融合が見られる。

市寸島比売命を祀る辺津宮の裏手の丘陵に、宗像の神が降臨したと云われる高宮がある。それは宗像大社の原初の祭場だと云われる。そこには"宗像の木"と呼ばれる神木が祀られ、その神木を崇める祭祀が行われていたと云う。
「日本書紀」の素戔嗚尊の記述にこうある「乃ち鬚髯を抜きて散つ。即ち杉に成る。又、胸の毛を抜き散つ。是、檜に成る。尻の毛は、是柀に成る。眉の毛は是櫲樟に成る。」これからすれば、樹木とは大地や山の毛という意味である。ちなみに樹木に生える苔は「木毛」とも書き表し「コケ」そのものは「垢」の意味もある事から、苔は樹木の垢でもあるが、ここでは樹木は毛であるのだから、苔とは頭髪に出るフケと同じものと捉えていいだろう。ただ全てひっくるめて、山に発生するもので、山そのものでもある。
先に紹介した市寸島比売命が嶋(山)に斎く女神であるなら、山そのものの神霊の依代でもある樹木に女神が斎く事は何ら不思議は無い。その宗像の木が祀られた高宮の近くに、やはり同時代に祀られた男根状の石の周辺に石で囲んだ環状列石古代祭祀場がある。その環状列石のある地は"八幡山"と呼ばれ、八幡神との関係があるらしい。
宇佐八幡の比売神は宗像の神と云われるが、先に記した様に「女神は木に斎き、男神は石に斎く。」の説の様に、同時代に市寸島比売命を祀る辺津宮の傍の高宮の樹木崇拝と、八幡山の環状列石が無関係とも考え辛い。つまり、八幡山の環状列石は宇佐の祀る男神である八幡神を迎える為に築かれた可能性があるのではなかろうか。宗像と宇佐との結び付きは、この市寸島比売命を祀る辺津宮周辺から始まったのではなかろうか。

以前「遠野物語拾遺10」を考えた時、アイヌのシランパによれば石よりも樹木の方が位が上だとなるが、これを本土の山神を基本として考えた場合、山神の依代のような毛でもある樹木と、山の瘤のような石とを比較すれば、確かに樹木の位の方が高いと云わざる負えない。例えば毛は髪(カミ)あり、神(カミ)通じるものだ。遠野には早池峯の女神から授かった剛毛により力を得た話などもある事から、毛は樹木であり、樹木は毛にもなるであろうと想定される。
「古事記」において岩戸に隠れた天照大神を迎える時「天の香山の五百つ真賢木を根こじにこじて…。」とあるのは根こそぎ引き抜いて、その樹木が生きながらリアルに山神の霊を迎えるという儀式だ。これは「日本書紀」神武天皇即位前紀「丹生の川上の五百筒の眞坂樹を拔取にして、諸神を祭ひたまふ。」また「山城国風土記」の「社の木を拔じて、家に植ゑて祷み祭りき。」とあるのも全て同じだ。「ギリシア神話」において大地の女神であるガイアに触れていれば、タイタン族は不死身であると同じように、大地と触れる樹木の根がある限り神事はリアリティを伴う。根は「ネ」であり「大地」の意味のある「ナ」の転だとされる。つまり樹木の根とは大地そのものである。それ故「遠野物語拾遺10」において出羽三山を信仰する羽黒修験との関係が深い天狗が、女神であるとされる山神と連動する樹木と背競べをした石を怒鳴ったのだろう。それだけ山神=女神という認識が広まっている証なのかもしれない。
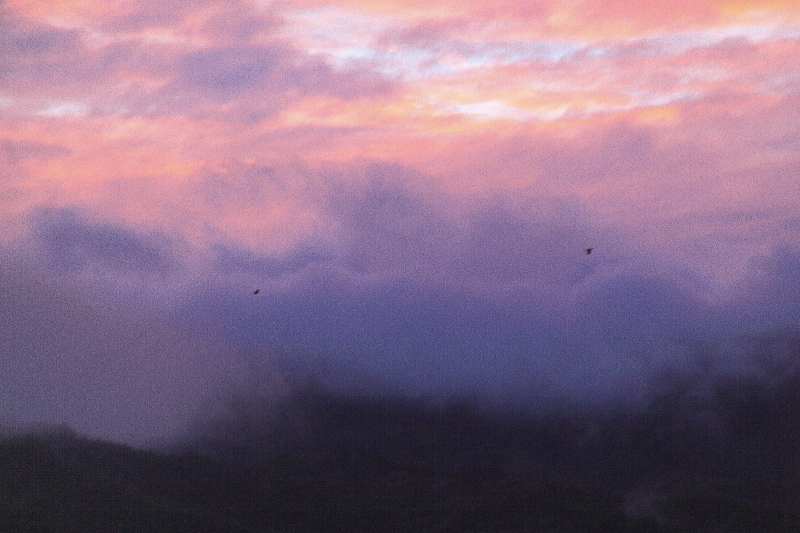
山は竜宮と繋がっていると云われ、全国に散らばる伝説にも山と海とが結びつく話が多い。海神宮の井に生える斎つ桂の木は、当然の事ながら水を湛えて山に自生する。遠野の物見山の桂から七体の観音像を彫って各地に祀った伝承も、池端の石臼の話も物見山にある池から登場する女の話もいろいろなバリエーションがあるのだが、宗像三女神の一人となる早池峯の女神と繋がる話がある事から、やはり海との繋がりを感じる。ましてや早池峯神社には宇佐から贈られた宝剣があった事からも、山の中の遠野には海との繋がりを感じさせる伝承が数多く残されている。これはつまり、海の民が山に移住し伝承を結んだものであると考える。実際に、山で発生した水は川を伝って海へと流れる。海の民が川を遡って山に辿り着いた場合、その山と海とを結びつける伝承を残したとしても何ら不思議が無いのだ。

再び、市寸島比売命を振り返ってみよう。宗像大社の社伝と、「古事記」「日本書紀」では、沖津宮・中津宮・辺津宮の祭神が名前も含めて迷走しているのが見受けられる。
1.「宗像大社社伝」 奥津宮→多紀理毘売命 中津宮→多岐都比売命 辺津宮→市寸島比売命
2.「古事記」奥津宮→多紀理毘売命 中津宮→市寸島比売命 辺津宮→多岐都比売命
3.「日本書紀」奥津宮→田心姫 中津宮→湍津姫 辺津宮→市杵嶋姫命
4.「日本書紀一書第一」奥津宮→澚津嶋姫 中津宮→湍津姫 辺津宮→田心姫
5.「日本書紀一書第二」奥津宮→市杵嶋姫命 中津宮→田心姫 辺津宮→湍津姫
6.「日本書紀一書第三」奥津宮→澚津嶋姫(市杵嶋姫命) 中津宮→湍津姫 辺津宮→田霧姫
この一覧を見てわかるのは、海の正倉院と呼ばれる奥津宮には湍津姫が鎮座したという事は無い。そして「古事記」において奥津島比売命とされる多紀理毘売命だが、その奥津島比売命は「日本書紀一書第一」「日本書紀一書第三」は市杵嶋姫命であり、更に「日本書紀一書第二」においても奥津宮に祀られている。「嶋に斎く女」としての市杵嶋姫命は、辺津宮でも奥津宮でも名前の通り重要な女神であるのがわかる。
宮島の厳島神社があるが「広島県史」によれば「按に、厳島神社の主神は、市杵嶋姫命なり、国史に之を伊都伎島といふ、他の二前の神は国史には伊都伎島中子天神、伊都伎島宗形小神と見ゆ、普通には、厳島神といへば、三女神を総括してこの名なる如きも、社格等に関する正式の場合には祭神は市杵嶋姫命一神の名のみ記さらる。」とあり、延喜式神名帳は厳島神社の祭神を一座としている事から、本来の宗像の神とは市杵嶋姫命であり、宇佐に祀られる宗像の比売神とは、やはり市杵嶋姫命であろう。考えるに高宮の樹木に降臨した市寸島比売命が八幡大神と結び付いたのが宇佐との結び付きであったろうが、恐らくそれ以前に水沼君が祀っていた水神を取り込んで市杵嶋姫命を含んで宗像三女神としたのではなかろうか。「記紀」の神代の卷に記される天照の言葉「汝三神、宣しく道中に降居して天孫を助け奉りて、天孫に祭かれよ。」との神勅は、まさに「記紀」での編纂時における、水沼君の信仰する水神を取り込んだ宗像が天孫に組する事の誓約では無かったか。水沼君の祀っていた水神は、恐らく多紀理毘売命か。多岐都比売命は瀬織津比咩であろうし、それは宮島の厳島神社から分霊された鹿児島県出水厳島神社の祭神が、市杵嶋姫命・田心姫・瀬織津比咩となっている事から、宗像三女神は「記紀」の編纂に合わせ宗像によって作られた三女神であろうと思うのだ。つまり本来の宗像神とは、市杵嶋姫命一座であったのだろう。