
以前、多岐都比売命について書いた。それは、櫟谷宗像神社をきっかけに、三女神の違和感を書いたものだった。その違和感が、今度は能登の奥津比咩神社と辺津比咩神社とに感じてしまう。
能登の沖に、舳倉島が浮かんでいる。そこに鎮座するのが、奥津比咩神社となる。祭神は多紀理毘売命。延喜式神名帳の鳳至郡の式内社「奥津比咩神社」に比定されている、古代から舳倉島に鎮座している神社であるようだ。神は人が祀ってこその神であるが、舳倉島にはシラスナ遺跡があり、3世紀の弥生末期の出土物があるよう。つまり、その時代には既に人が住んでおり、神を祀っていたのだろう。説によれば、宗像の沖ノ島と同じように、大陸との交流をしていた中継の島であるとも云われる。

また別に、延喜式神名帳にこの奥津比咩神社と併記されている市寸島比売命を祭神とする辺津比咩神社は、現在の輪島にある重蔵神社であると云う。しかし現在の重蔵神社は形骸化が進み、雑多な神々が祀られ原初の祭神が曖昧になっているようだ。
単独で祀られる、多紀理毘売命と市寸島比売命であるが、何故か多岐都比売命を単独で祀る神社は無い。実は、日本全国でも多岐都比売命を単独で祭祀する神社が無いのは何故だろうか?
そして、この能登に祀られる田心姫と市寸島比売命だが、それを総括するかのように三女神として祀る神社は、羽咋郡志賀町の意富志麻神社であるようだ。

宗像三女神の神名を見ていて違和感を覚えたのは当初、市寸島比売命だった。多紀理毘売命と多岐都比売命は、ウィキペディアの説明によれば「神名の「タキリ」は海上の霧の事とも、「滾(たぎ)り」(水が激しく流れる)の意で天の安河の早瀬のこととも解釈される。」
そして多岐都比売命も「神名の「タギツ」は「滾(たぎ)つ」(水が激しく流れる)の意で、天の安河の早瀬の事と解釈される。」とあり、殆ど同じ意味の神名である事がわかる。それからすれば、市寸島比売命の神名の意味は「神に斎く島の女性(女神)という意味。」であり、三女神の中で異彩を放っているように思えた。しかし今、もう一度考えてみると、市寸島比売命は辺津宮に鎮座し、自らの役目を守っている神であると感じる。つまり今まで、宗像三女神はA(多紀理毘売命)、B(多岐都比売命)、C(市寸島比売命)であると思っていた。しかし神名の意味を踏まえると、実はA(多紀理毘売命)、A´(多岐都比売命)、B(市寸島比売命)であるのが理解できる。能登に古代から、多紀理毘売命と市寸島比売命の二柱の女神が祀られていたように、この二柱の神で、用は為すのである。つまり多岐都比売命は余分な神であった。市寸島比売命が末の妹と言われていながら、何故か「古事記」の誓約のシーンで、三女神のうち最後に生まれたのが多岐都比売命であったのも不可解であった。
京都の櫟谷宗像神社に祀られる宗像の女神も、多岐都比売命を除いた多紀理毘売命と市寸島比売命であったのも本来、多岐都比売命は後から付け加えられ宗像三女神という観念としての女神誕生に必要であった為だろう。逆に言えば、宗像三女神という観念の三女神を誕生させる為に多岐都比売命は本来の神名を伏せられ、多岐都比売命として祀られた可能性があるのではなかろうか。
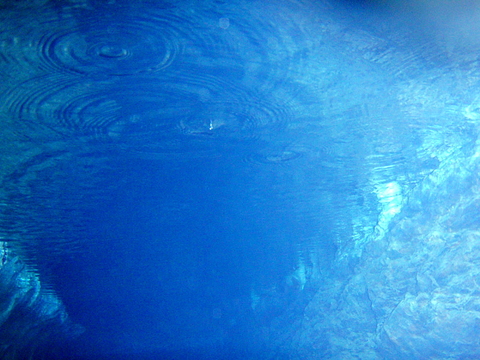
舳倉島の奥津比咩神社に宗像大社の影響はあったのか?宗像三女神の多紀理毘売命の神霊が勧請されて、奥津島比売命神社となったのかは、今のところはっきりしていないらしい。「武内社調査報告」によれば「大陸との航路の要衝を為す舳倉島に航海の安泰を祈る国家神として崇信されるに至ったものと考えられる。ただし、これが直ちに筑前の宗像三神のものとは断定できない。」とされているようだ。
また「舳倉島シラスナ遺跡発掘調査報告書」では、気になる記述がある。「延喜式神名帳では奥津比咩神社、辺津比咩神社と併記され、一括記載されている宗像三女神とは対照的な扱いを受けている。」と。つまり能登においては、多紀理毘売命と市寸島比売命の二柱祭祀が独立しており、三女神を強調する宗像三女神とは一線を画していたという事である。これから見ても、多岐都比売命とは宗像に飲み込まれた別の神であったのではないのか?と考えてしまうのだ。

となれば、その答えは京都の櫟谷宗像神社に見られるように、多紀理毘売命と市寸島比売命に、同じ京都の大井神社の祭神である八十禍津日神であり、別名瀬織津比咩が多岐都比売命に名を変えて宗像三女神にされてしまった可能性は高いのではなかろうか。