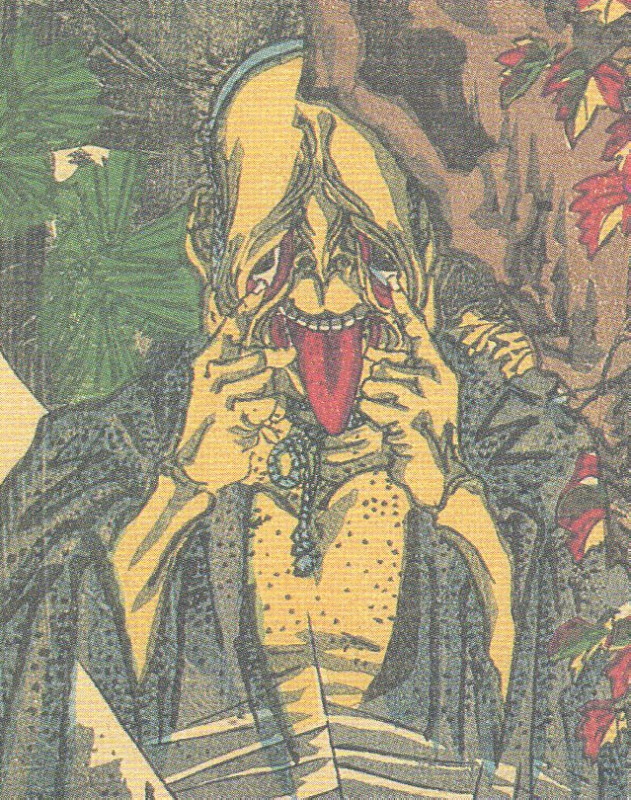
これは維新当時のことと思われるが、油取りが来ると言う噂が村々に拡がって、夕方過ぎは女子供は外出無用との御布令さえ庄屋、肝いりから出たことがあったそうな。毎日の様に、それ今日はどこ某の娘が遊びに出ていて攫われた、昨日はどこで子供がいなくなったという類の風説が盛んであった。ちょうどその頃川原に柴の小屋を結んだ跡があったり、ハサミ(魚を焼く串)の類が投棄ててあった為に、油取りがこの串に子供を刺して油を取ったものだなどといって、ひどく恐れたそうである。油取りは紺の脚絆に、同じ手差をかけた人だといわれ、油取りが来れば戦争が始まるとも噂せられた。これは村のたにえ婆様の話であったが、同じ様な風説は海岸地方でも行われたと思われ、婆様の夫冶三郎爺は子供の時大槌浜の辺で育ったが、やはりこの噂に怯えたことがあるという。
「遠野物語拾遺234」
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
佐々木喜善「聴耳草紙」に「油採り」という話が紹介されているが、そこではナマハゲの伝承に似て、太ったナマケモノには油取りが来るような話となっている。実はこれ、逃竄譚といわれるもので、怠け者などが旅先で歓迎されるが恐ろしい目に遭って逃げ助かる話であり、「三枚の御札」の系統に属する話である。

この「遠野物語拾遺234」の話は、画像の辷石谷江から聞いた話であるよう。この中で「油取りが来れば戦争が始まる」とされているのは、明治六年各地で起こった徴兵制に絡む都市伝説からであるようだ。徴兵に応じると外国に連行され、生き血を搾り取られるとの噂が拡がり一揆にも発展したという事件があった。この明治の都市伝説が油取りと重なり、恐れられたようである。
考えて見れば、この現代でも"口裂け女"の都市伝説があたかも事実の様に日本列島を駆け巡った。地域によっては、口裂け女が怖い為に登校拒否になったり、通学に際して大人達が子供達を守る為に、登下校を見守ったりした。つまり流言が事実と認識された為であった。明治時代の生き血を搾り取られる流言もまて信じられたからこそ、不安が高まり一揆にまで発展したのを考えれば、リアリティ溢れる流言は、人の心を乱してしまうという事だろう。油取りの話も、生き血を搾り取る話も、時代的にはそう変わりの無い時代である。つまり、どこかでこの残酷な油取りの話は、根底で生き血を搾り取る話と繋がってそうな気がする。
油取りのイメージ的には、処刑の一つである磔ではないだろうか。磔は残酷で、体を槍などで刺して血が流れるのだが、すぐには死なずに放置されるようだ。それが血を搾り取る、もしくは油を取る様子に似てるのでは無いだろうか。「聴耳草紙」での「油採り」の話は、逆さまに吊り下げて目鼻口から滴る人油を採るシーンがある。これは、逆さ磔と同じものだと感じる。逆さ磔は、罪人を最大限に苦しめてジワジワ殺す刑罰だという。逆さに吊るされると血液が脳にたまり、脳浮腫をおこしてすぐに死んでしまう為、こめかみの静脈を切り、少しづつ血が滴る様にして長く苦しんで死ぬようにしたのが、逆さ磔であった。この時、その磔された罪人の下には、多量の血が溜まったと云うが、これが油取りのイメージに繋がる気がする。いや、断言しよう。公開処刑である磔を見て来た日本人に刻まれたトラウマが生み出したのが、油取りの都市伝説であったと。